![[ドキュメンタリー]がスキ!](http://madstudents.tokyo/wp/wp-content/uploads/2018/06/mimg_00007-pc.jpg)
![[ドキュメンタリー]がスキ!](http://madstudents.tokyo/wp/wp-content/uploads/2018/06/mimglow_00007-pc.jpg)
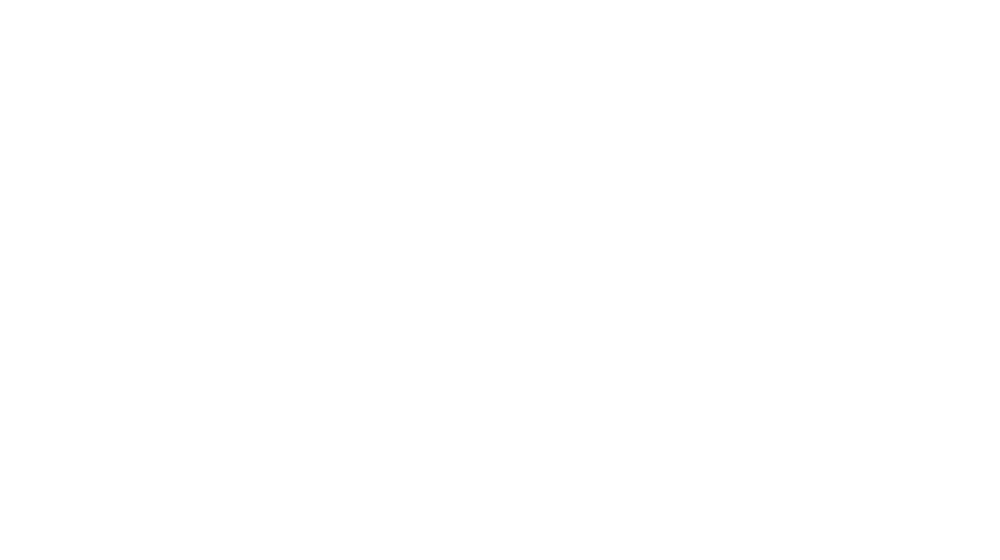
[ドキュメンタリー]
がスキ!
- profile
久保田徹
- 慶應義塾大学 法学部政治経済学科 4年。
ミャンマーでの映画製作のために半年休学し、ドキュメンタリー映画を制作。ロヒンギャ難民を取材したドキュメンタリー映画「Light up Rohingya」にて監督を務め、国際平和映像祭 AFP通信賞、学生部門賞を受賞。国際問題と向き合い、伝える学生団体S.A.Lに所属。現在、現地で偶然出会ったミャンマー人のジャーナリストとともにミャンマーでのプロジェクトに取り組んでいる。(以上は取材当時)
『テレビで目にする憧れのあの人とお近づきになりたい!』あなたも一度くらい、そんな気持ちになったことがあるだろう。そんな時、映像の中の人をリアルに映し出すドキュメンタリーは、あなたの欲求を少しだけ解消してくれるはずだ。
しかし、今回の主人公である久保田徹さんはドキュメンタリーを「あんなの真実ではない」とバッサリ。自らが作ったドキュメンタリー作品で、受賞歴もある彼がなぜそんなことを言ったのか。その背景を探っていくと、ジャーナリストとしての彼の一面が見えてきた。
chapter 1
真実とは、誰かが作るもの

— ドキュメンタリーと調べると「虚構のない事実を記録した映像」と定義されることが多いです。いわゆるノンフィクションと呼ばれるタイプの映像のはずですが、なぜ真実ではないとおっしゃるのですか?
混乱させてしまうかもしれませんが、ドキュメンタリーとは必ずしも、編集なく、真実だけを表現しているものではないということです。いくらリアルを切り取った映像に見えても、多くの場合、撮影者や編集者の都合が反映されてアウトプットされています。虚構を中心に作られたものがフィクションであり、事実を中心に作られるのがノンフィクションということでいいのだと思います。
— なるほど。では、ここからはその定義に基づいてお話を聞かせていただければと思います。久保田さんが以前作られたドキュメンタリーは、ミャンマーのロヒンギャ難民を取り上げたものでした。なぜあのような映像を手がけられたのですか?
まず、国際問題について強い関心がありましたから、なにかの媒体を通じて取り上げられないかと考えていました。同時に、ドキュメンタリーにも興味があったので、媒体として採用したのですが、採用した裏テーマとして「ドキュメンタリーが真実ではない」という話と関係があったりします。
— 話せる限りで裏テーマをお願いします。
大丈夫ですよ、全部お話しします笑
先ほども言った通り、ドキュメンタリーは全てが真実だけで構成されているわけではありません。作り手が、一番取り上げたいコンセプトを明確に伝えるために、数多くの編集が施されています。ある意味、事実と言い切れないと言われればそれまでです。
しかし、だからこそ、「世の中には絶対的な真実なんて存在しない」ということを視聴者に訴える媒体として最適ではないかと思ったのです。
また、一時期流行った『Post truth』に象徴されるように、現代はかつてなく真実というものが曖昧な存在となっていますよね。メディアが個人に細分化されたことによって、「真実は作れる」ものになってしまいました。
— うーむ。たしかに。
詳しくは説明しませんが、ロヒンギャ難民は国を追われ、大量虐殺されている人々です。彼らを取り上げたニュースはミャンマーでも多く報道されますが、自分ごとにしたくない多くの国民はそれを偽りだと思い込んでいます。
つまり、虐殺は事実ですが、それを嘘だと思い込んでいる人たちで溢れるミャンマーの様子は、まさに「世の中には絶対的な真実なんて存在しない」「真実は作れてしまう」という現代のジャーナリズムを象徴していると感じたのです。
だから、ドキュメンタリーが最適なアウトプットだと思いましたし、ドキュメンタリーでロヒンギャ難民を取り上げることでメッセージ性が高まると考えたのです。

chapter 2
分断の時代に、中立の存在で居続ける

— 久保田さんがドキュメンタリーを手がけられたのには、そんな深い理由がおありだったのですね。真実、という言葉を多用されていましたが、今の時代、真実を語ろうとすると、都合の悪い人によって排除されるケースが多いように思えます。
僕もそう思いますよ。
なんていうか…真実が作られる、ということは分断を促進することに繋がりませんか?あるコミュニティにとってはAという真実が都合よくて、別のコミュニティにとってはBという真実に捻じ曲げた方が都合がいい、みたいな。
— アメリカの大統領選挙が思い浮かびます。
多様性という割には、現代は分断の激しい時代ですよね。そんな時代では、中立的な意見を持つ人や、発信する人は誹謗中傷の対象になります。白と黒をはっきりと分けようとする傾向があるので、ドキュメンタリーの役割はその実情に対するアンチテーゼでもあるかもしれません。
アメリカは例としてとてもわかりやすいのですが、完全に分断されてしまった者同士は議論しようとしませんよね。白と黒がはっきりとしているということは、そこに議論の余地はないということ。
僕の映像でいう「世の中には絶対的な真実なんて存在しない」というコンセプトのように、ドキュメンタリーはリアルな映像を通して、取り上げた問題について考えるきっかけを視聴者に提供する役割がありますから。
— ドキュメンタリーという中立的なメディアを生み出す久保田さんは、ポジションとしても視聴者と映像で取り上げる人との中間に居続けています。Mediaの語源はラテン語で『medium』、つまり中間という意味。ズバリ、ですね。
その通りですね。言われてハッとしました。
中立的な意見を持ち、勇気を持って議論の種を投げる人が、今の世の中には必要な気がしています。
ジャーナリストがならないといけませんよね。

chapter 3
新時代のジャーナリストが世界を変える

— 久保田さんは映像で、本当に世界を変えてしまいそうですよね。すごいパッションを感じます。
ありがとうございます。
でも、『Light up Rohingya』(久保田徹/2016)が受賞したとき、「偶然撮れた悲惨な映像が人の心を動かして、受賞に繋がったのだ」とすごく悩んだんですよ。見方によってはロヒンギャ難民の不幸を出汁にして、僕が表彰されているわけですから。ジャーナリズムはそういう側面が少なからずあると思います。
— でも、ジャーナリストの性質上、仕方がないのでは?
これまではそれで良かったのだと思います。
ジャーナリストは発信者である一方、世界でなにかが起こってからその事実について考察する受け手でもありましたから。しかし、その悲惨な事実を知っているのにただ発信するだけでいいかというと、僕はそれではいけないと思うのです。
— 新時代のジャーナリストには、なにができるのでしょう。
世界を中立的に見ているからこそ、自らの手で理想の世界を実現していくことができると思っています。『Light up Rohingya』はその始めの一歩です。実際、あの映像を見た多くの人からもっと色んなところで上映してほしいという声や、国際問題に関する意識が大きく変わったという声を多くいただきました。次は、当事者であるミャンマーの国民の意識を変えていかなければいけませんし、すでに現地の映像クリエイターとプロジェクトを始めています。
— 心から素晴らしいと思います。でも、そのためには多くの人を巻き込んでいかなければいけませんよね。
はい。
だから、新時代のジャーナリストにはただ発信するだけでなく、自分でメディアを生み出し、それによって実現したい世界がどんなものなのかを、他人に明確に伝えられる能力が必要です。説明できなければ、人は動きません。
正義感ではないのです。理想の世界を実現したいというのは、シンプルに自己実現でしかないのですが、それによって本当に世界が変わっていくのであれば、ロヒンギャ難民たちも心から喜んでくれるのではないでしょうか。
そして、そのとき僕の葛藤も解消されているはずです。

「現代のような情報過多な社会において、私たちは常になにかしらのメディアを目にしているが、本当に受け取ってばかりでいいのだろうか。そう、強く考えさせられる取材だった。彼と話していると、間髪なく現代のジャーナリズムにおける深い考察が飛び出してくるが、それはきっと自ら発信側になることで、自分の身近な環境にも変化が起こせることを身をもって知っているからかもしれない。
ちなみにもちろん、この記事はノンフィクション。真実を捻じ曲げるような編集はしていない。むしろ、彼のこれからの挑戦を応援していける記事になっていれば幸いだ。